通常の教科書だと大体中2の最後が中3の最初に学ぶ受動態。
ここまで英語で生き残ってる子も多くはないが
その少ない生存者も、この受動態で躓く子は多い。
結構多い印象だ。
まず、能動態の日本語から指導はスタートする。
太郎は毎日このペンを使う
そして、この状況は変えずに
「○○される」となるように日本語を変える。
このペンは毎日太郎によって使われる
となる。
ここで
太郎は毎日このペンを使われる
としてしまう子がいるが、それは状況が変わっちゃってるよね、と指導。
あくまでも、目の前で起きていることは変えずに、
動作主と動作を受ける側を入れ替わるんだと染み込ませる。
この日本語段階で躓くことは絶対に避けたい。
そして
ここからが危険ゾーン
通常、テキストとかに書いてある説明は
図解
のようなものになる。
Taro uses this pen every day.
この文の目的語を文頭に主語として「移動」させ、
動詞の部分を「be動詞 ➕ 過去分詞」に変えて
主語だったものを「by 動作主」という形にして「移動」させる
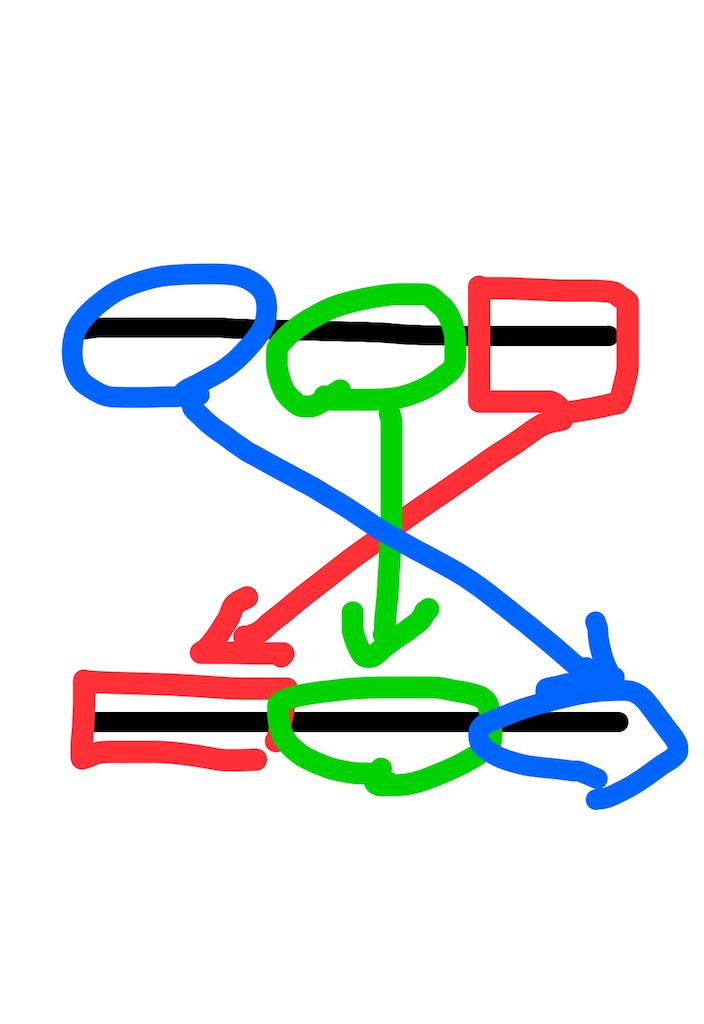
こんな「図解」つきで。
これまで、こんな図解なんて出てきてないのに、
受動態でいきなりの図解…
「なにそれー」
ってなるか
「あー、このやり方で変えれば良いのか」
と納得するか
これが大体一般的な受動態の指導法。
納豆英文法と全然違う!
受動態の文は、能動態の文を「変化」させたものじゃなくて
スタートからオリジナルの文としてそこに存在してるんだよ。
そうでしょ?
日本語だって、まず能動態の文を考えてから、それを「入れ替え」て受動態の文を作るなんてことはしないよね?
すごく当たり前のことなんだけど
なぜか受動態の単元には奇怪な「図解」が出てくる。
おそらく文法問題で「態の変換」が出るからかな。
どうなんだろう。